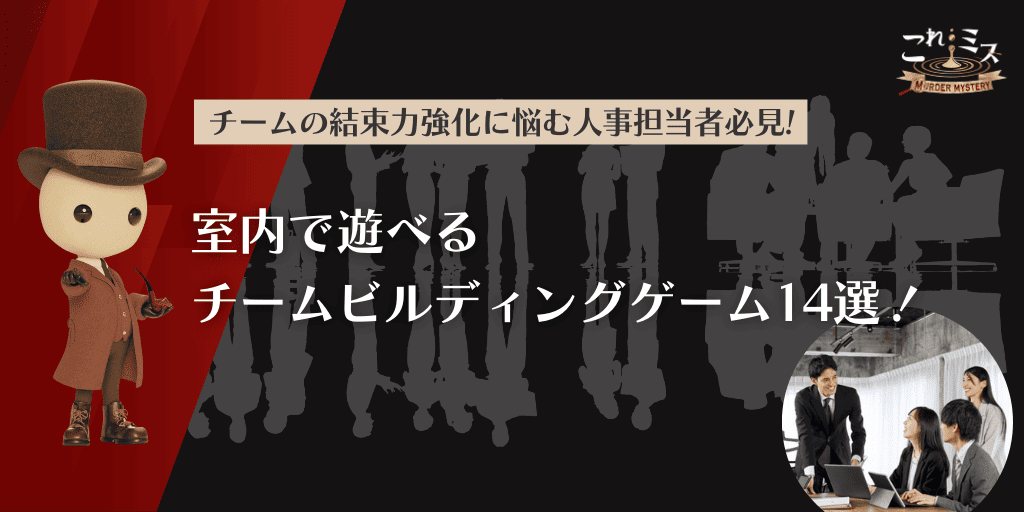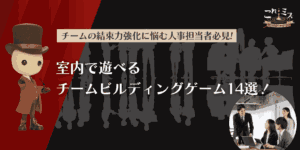チームの結束力強化や研修活性化に悩む人事担当者・リーダーの方へ。
この記事では、室内で実施できる効果的なチームビルディングゲームを目的別に紹介します。
アイスブレイクからコミュニケーション、協調性、チームワーク向上まで、状況に合わせたゲーム選びのポイントも解説するので、チームの課題解決に役立つ実践的な情報としてぜひご活用ください。
>>アイスブレイクをするのにおすすめの室内ゲームをすぐに知りたい方はこちら
>>コミュニケーションを高めるのにおすすめの室内ゲームをすぐに知りたい方はこちら
>>協調性を高めるのにおすすめの室内ゲームをすぐに知りたい方はこちら
>>チームワークを向上させるのにおすすめの室内ゲームをすぐに知りたい方はこちら
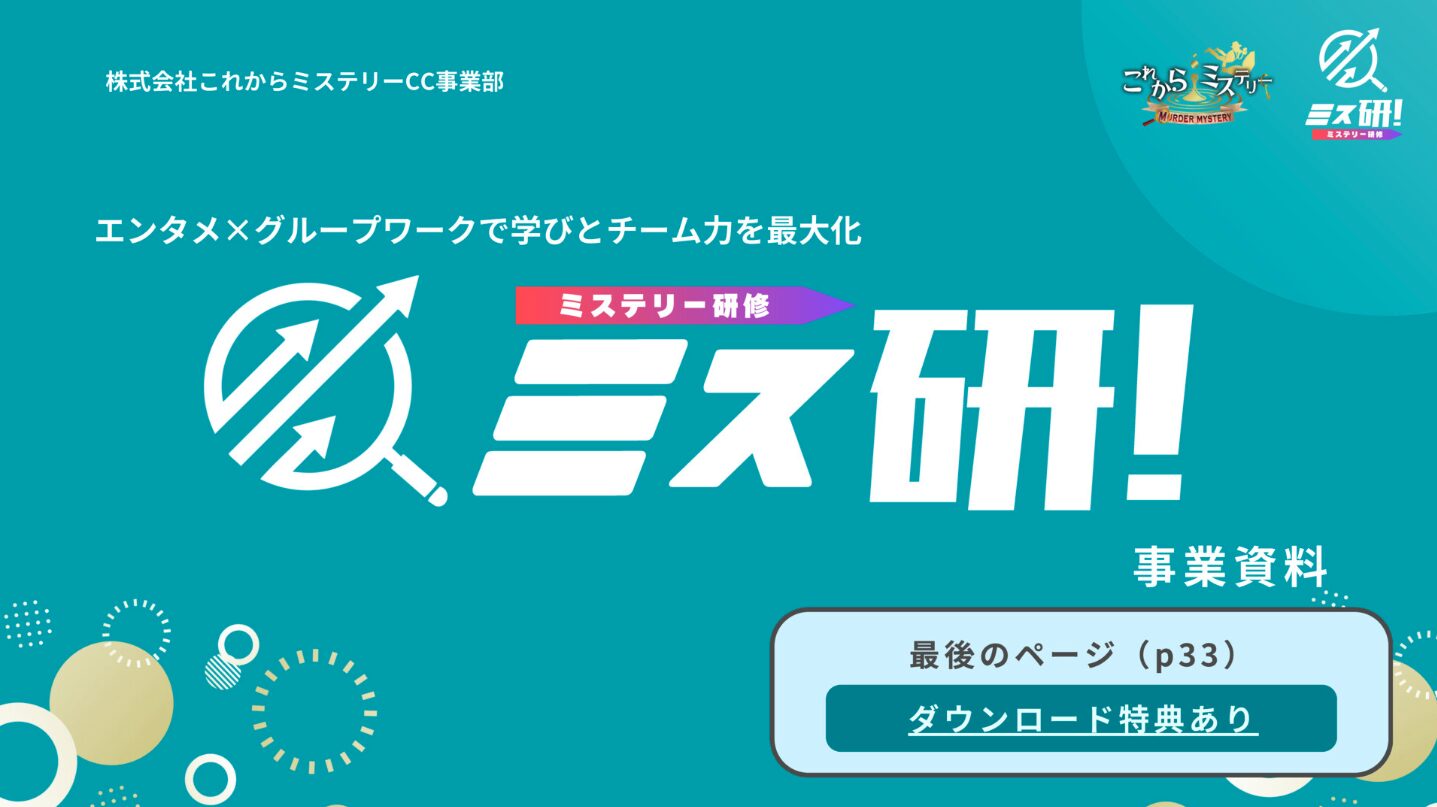
- これからミステリーは飯田祐基とヒカルがタッグを組んだマーダーミステリー専門の企業
- マーダーミステリーを絡めた「企業研修」や「企業PR」も可能!
- 社内コミュニケーションの活性化や企業の認知拡大におすすめ!
\認知を広げたいあなたに/
チームビルディングとは

チームビルディングとは、組織内のメンバー同士の信頼関係を構築し、協力して目標を達成するための能力を高めるプロセスです。単なる親睦会や飲み会とは異なり、目的を持った活動を通じてチームの一体感や生産性を向上させる取り組みといえるでしょう。
企業や学校などの組織では、メンバー間の関係性が業績や成果に大きな影響を与えます。良好な人間関係があれば、コミュニケーションがスムーズになり、問題解決能力も高まります。
チームビルディングを行う主な目的は、メンバー間の壁を取り払い、互いの強みや特性を理解し合うことにあります。特に新しいプロジェクトの開始時や組織改編後には効果的な手法として注目されています。
【アイスブレイク編】チームビルディングにおすすめの室内ゲーム

チームビルディングの最初のステップとして、メンバー間の緊張をほぐし、コミュニケーションの土台を作るアイスブレイクは非常に重要です。ここでは、室内で簡単に実施できる効果的なアイスブレイクゲームを紹介します。
初対面のメンバーや普段あまり話さないメンバー同士の緊張をほぐし、場を和ませるアイスブレイクは、チームビルディングの第一歩です。ここでは、室内で手軽に実施できるアイスブレイクゲームを紹介します。
バースデーライン
バースデーラインは、言葉を使わずに全員が誕生日順に一列に並ぶゲームです。参加者は誕生月と日を身振り手振りで伝え合い、1月1日から12月31日までの順に並びます。このゲームでは会話を禁止するため、非言語コミュニケーションの重要性に気づくきっかけになります。
所要時間は10分程度で、特別な道具も必要ないため、急な会議の前や研修の導入部分に適しています。参加者が並び終わったら、実際に誕生日を確認していくことで、間違いがあれば笑いも生まれるでしょう。
このゲームを通じて、言葉以外でも効果的に意思疎通できることや、全員で協力して一つの課題を解決する体験ができます。また、誕生日という個人情報を共有することで、自然と距離が縮まる効果も期待できるのです。
2つの真実と1つの嘘
「2つの真実と1つの嘘」は、自己紹介を兼ねた簡単なゲームです。各参加者が自分自身について3つの事実を述べますが、そのうち2つは本当のことで、1つは嘘という形式で進行します。他のメンバーはどれが嘘かを当てる必要があります。
このゲームの魅力は、互いの意外な一面を知るきっかけになる点にあります。普段は知ることのない趣味や経験、特技などが明かされることで、新たな会話のきっかけが生まれることも少なくありません。
実施する際のコツとしては、あまりにも簡単に見破られる嘘ではなく、ちょっと信じられそうな嘘を混ぜるよう伝えることが大切です。全員の発表後、最も多く正解した人や、最も見事な嘘をついた人を表彰すると、さらに盛り上がりを見せるでしょう。
共通点探しゲーム
共通点探しゲームは、小グループに分かれて、チーム内で意外な共通点を見つけ出すアクティビティです。「好きな食べ物」や「出身地」といった一般的な項目ではなく、「同じ月に旅行した場所がある」「似たようなトラウマ体験がある」など、少し掘り下げた共通点を探すことがポイントです。
制限時間を5分程度設け、その間にできるだけ多くのユニークな共通点を見つけたチームが勝利となります。共通点を見つける過程で、自然と深い会話が生まれ、お互いへの理解が深まるでしょう。
このゲームの効果として、普段の業務では見えない個人的な側面を知ることができ、共感や親近感が育まれます。また、「私たちって意外と似ているんだ」という発見が、チーム内の一体感を高めることにもつながります。
【コミュニケーション編】チームビルディングにおすすめの室内ゲーム

効果的なコミュニケーションはチームの成功に不可欠です。ここでは、情報伝達や意思疎通の能力を高める室内ゲームを紹介します。これらのゲームを通じて、メンバー間の意思疎通がスムーズになり、より強固なチームワークの基盤を築くことができるでしょう。
人狼ゲーム
人狼ゲームは、プレイヤーが「村人」と「人狼」に分かれ、村人チームは人狼を見つけ出し、人狼チームは正体を隠しながら村人を減らしていくコミュニケーションゲームです。限られた情報の中で推理し、説得力のある主張を展開する能力が試されます。
このゲームの最大の魅力は、言葉を通じた駆け引きやロジカルシンキングを実践できる点にあります。発言の矛盾を見つけたり、非言語的な反応から相手の本心を読み取ったりする観察力も養われるでしょう。
ビジネスの場面でも、限られた情報から最適な判断を下す場面は多々あります。人狼ゲームで培った分析力や説得力は、会議での発言や交渉の場面にも活かすことができるのです。
野球のポジション当てゲーム
野球のポジション当てゲームは、チーム内の役割認識とコミュニケーションを強化するユニークなアクティビティです。参加者は自分が思う「チーム内での自分のポジション」を考え、その理由を説明します。一方、他のメンバーは各人に対して「この人はこのポジションだろう」と予想し、その理由も共有します。
ピッチャーやキャッチャー、内野手や外野手など、野球のポジションには特徴があります。たとえば、リーダーシップを発揮する人はピッチャー、サポート役に徹する人はキャッチャーというように例えることができるでしょう。
このゲームを通して、自己認識と他者からの評価のギャップに気づくことができます。また、「なぜそう見られるのか」という理由を聞くことで、自分の言動や振る舞いがチームにどう映っているかを知る貴重な機会となるのです。
ジェスチャーゲーム
ジェスチャーゲームは、言葉を使わずに特定の言葉や概念を伝えるアクティビティです。チームを2つに分け、一方のメンバーが与えられたお題を身振り手振りだけで表現し、もう一方のメンバーがそれを当てるという流れで進行します。
制限時間内にいくつのお題を正確に伝えられるかを競うことで、自然と盛り上がりを見せます。ビジネス用語や業界特有の概念をお題にすると、業務理解も深まり一石二鳥です。
このゲームの価値は、言語に頼らないコミュニケーション能力の向上にあります。実際のビジネスシーンでも、言葉だけでなく表情やジェスチャーなどの非言語要素がメッセージの60%以上を占めるとされています。
明確に伝えるための工夫や、相手の意図を汲み取る観察力は、日常のコミュニケーションでも大いに役立ちます。特に異なる言語や文化背景を持つメンバーが混在するチームでは、非言語コミュニケーションの重要性が増すでしょう。
【協調性編】チームビルディングにおすすめの室内ゲーム

チーム内の協調性を高めるゲームは、メンバー同士が互いに協力し、共通の目標に向かって力を合わせる姿勢を養います。ここでは、室内で実施できる協調性を高めるゲームを紹介します。これらのアクティビティを通じて、互いを尊重し、支え合う関係性を構築しましょう。
マーダーミステリー

マーダーミステリーは、参加者それぞれが物語の登場人物となり、与えられた役柄や情報をもとに推理や交渉を行うロールプレイングゲームです。架空の殺人事件を解決するという設定のもと、各自が持つ情報を共有し合い、グループで真相に迫っていきます。
このゲームの最大の特徴は、全員が主役であり、同時に互いの協力者であるという点です。一人ひとりが持つ断片的な情報を組み合わせなければ、事件の全容は見えてきません。個々の発言や行動が全体の進行に影響するため、責任感と参加意識が自然と高まります。
ビジネス環境では、異なる部署や立場の人間が持つ情報や視点を共有し、総合的な判断を下す場面が多々あります。マーダーミステリーを通じて培われる「情報共有の大切さ」や「多角的な視点での分析力」は、実際の業務にも直結する貴重なスキルとなるでしょう。
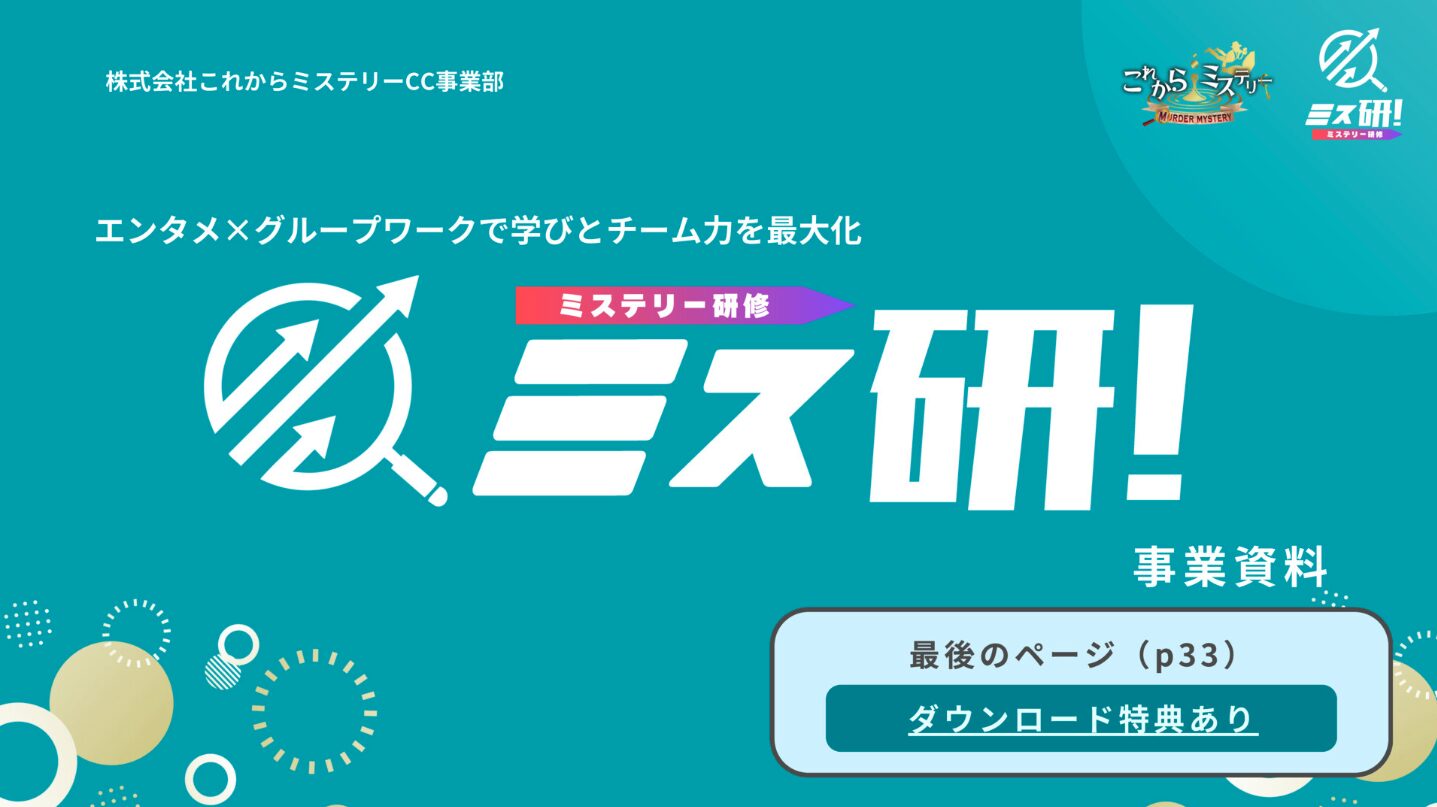
- これからミステリーは飯田祐基とヒカルがタッグを組んだマーダーミステリー専門の企業
- マーダーミステリーを絡めた「企業研修」や「企業PR」も可能!
- 社内コミュニケーションの活性化や企業の認知拡大におすすめ!
\認知を広げたいあなたに/
ペーパータワー
ペーパータワーは、チームごとに同じ数の紙とテープだけを使って、できるだけ高いタワーを制限時間内に作るというシンプルなゲームです。高さと安定性を両立させるには、チーム全体の協力と戦略が必要となります。
素材が限られているからこそ、アイデアの出し合いや役割分担が重要になります。誰かが独断で進めるのではなく、設計、制作、検証など、それぞれの得意分野を活かした分業制が効果的です。
このゲームでは、計画段階から実行、そして問題発生時の臨機応変な対応まで、実際のプロジェクト進行と同じプロセスを短時間で体験できます。タワーの完成後には「なぜこのチームが高く作れたのか」「どのような協力体制が効果的だったか」などを振り返ることで、日常業務にも活かせる気づきが得られるでしょう。
マシュマロ・チャレンジ
マシュマロ・チャレンジは、スパゲッティ、テープ、紐、そしてマシュマロを使って、できるだけ高い自立構造物を作るゲームです。チーム全員で知恵を出し合い、限られた素材で最適な構造を考える必要があります。
このゲームの興味深い点は、幼稚園児のチームが企業の幹部チームよりも高い塔を作れることがあるという事実です。子どもたちは失敗を恐れず何度も試行錯誤するのに対し、大人たちは完璧な計画を立てようとして行動が遅れがちになります。
実務においても、計画ばかりに時間をかけるより、小さな実験を繰り返しながら進める「プロトタイピング」の重要性が認識されています。失敗を恐れず、チーム全体で学びながら進化していく姿勢は、変化の激しい現代のビジネス環境で特に重要となるでしょう。
ドミノ
ドミノは、チームで協力して複雑なドミノの配列を作り上げ、最後に一斉に倒れる様子を楽しむゲームです。単純なようでいて、全体のデザイン、細部の調整、そして一人の失敗が全体に影響するという点で、優れたチームビルディングツールとなります。
計画段階では全体のビジョンを共有し、実行段階では細心の注意と丁寧さが求められます。また、誰かがドミノを誤って倒してしまった場合も、責めるのではなく全員で再構築するという経験は、失敗への対応力を養います。
完成したドミノが次々と倒れていく瞬間の達成感は格別です。地道な作業の積み重ねが壮大な結果につながるという体験は、長期的なプロジェクトにおけるモチベーション維持の大切さを実感させてくれるでしょう。
【チームワーク編】チームビルディングにおすすめの室内ゲーム

効果的なチームワークは、個々の能力を最大限に引き出し、チーム全体のパフォーマンスを向上させます。ここでは、メンバー間の連携や信頼関係を強化する室内ゲームを紹介します。これらのアクティビティを通じて、一人では達成できない成果を生み出す喜びを共有しましょう。
流れ星ゲーム
流れ星ゲームは、参加者が円形に並び、一つのボールを隣の人に素早く回していくシンプルなゲームです。スタート時は1つのボールですが、徐々にボールの数を増やしていくことで難易度が上がっていきます。全員が協力して、どれだけ多くのボールを落とさずに回せるかを競います。
このゲームの面白さは、チーム全体のリズムと集中力が試される点にあります。誰か一人でもタイミングが合わなければ、全体の流れが乱れてしまいます。また、ボールの数が増えるにつれて、先を見据えた準備や素早い対応力も求められるようになります。
実際のビジネスシーンでも、複数のプロジェクトやタスクが同時進行する状況は珍しくありません。このゲームで培われる「全体を見渡す視野」や「次の行動への準備」は、日常業務の効率化にも直結する重要なスキルです。
ヘリウムリング
ヘリウムリングは、長い棒(または紐)をチーム全員の指の上に置き、全員で協力して棒を地面に下ろすというパラドックス的なゲームです。個々の力が働くと逆に棒が上がってしまうため、完全な協調性が求められます。
一見単純そうに見えるこのチャレンジですが、実際にやってみると非常に難しいことに気づくでしょう。誰かが少しでも指に力を入れると棒は上昇し、かといって力を抜きすぎると棒が落下してしまいます。
このゲームを通じて学べるのは、チームの中での「適切な力加減」の重要性です。強引なリーダーシップも、過度な遠慮も、チーム全体のバランスを崩す原因となります。互いの動きを感じ取りながら、全体として調和のとれた行動を取ることの大切さが体感できるでしょう。
ピンポン玉リレー
ピンポン玉リレーは、スプーンに乗せたピンポン玉をチーム全員でリレーしていくゲームです。ただし、手は使わず、スプーンをくわえた状態で次の人にパスしなければなりません。玉を落とさずに、いかに速くゴールするかを競います。
このゲームの難しさは、個人の技術だけでなく、パスの瞬間の息の合わせが重要となる点です。自分のペースだけを考えるのではなく、相手の状況を見て適切なタイミングで動く必要があります。
職場においても、業務の引き継ぎや連携が滞りなく行われることの重要性は言うまでもありません。このゲームで身につく「相手に合わせる柔軟性」や「確実な受け渡しの大切さ」は、組織内のワークフローをスムーズにする上で非常に有益な姿勢となるでしょう。
しっぽ取りゲーム
しっぽ取りゲームは、参加者がそれぞれ自分の「しっぽ」(布や紐を腰に付ける)を守りながら、他の人のしっぽを取るというアクティブなゲームです。室内でも十分なスペースがあれば実施可能で、体を動かすことでエネルギッシュな雰囲気が生まれます。
このゲームをチームビルディング向けにアレンジするには、個人戦ではなくチーム戦にするのがポイントです。例えば、チームのしっぽを全て守り切った、あるいは最も多く敵チームのしっぽを集めたチームが勝利、というルールにします。
チームプレーにおける「個人の役割理解」と「全体戦略の重要性」が学べるゲームです。攻撃に特化するメンバー、守備を固めるメンバー、状況に応じて臨機応変に動くメンバーなど、それぞれの特性を活かした役割分担が自然と生まれます。
企業活動においても、個々の社員が自分の強みを理解し、チーム全体の目標達成のために最適な役割を果たすことが成功への鍵となります。このゲームを通じて、多様性を活かしたチーム編成の重要性を体感できるでしょう。
室内チームビルディングゲームに関するよくある質問

チームビルディングゲームを実施する際には、様々な疑問や不安が生じるものです。ここでは、特に多く寄せられる質問とその回答をまとめました。実施前の参考にしてください。
少人数で遊べるチームビルディングゲームは?
少人数(3~5人程度)のチームでも効果的に実施できるチームビルディングゲームには、いくつかの選択肢があります。特におすすめなのが、全員の積極的な参加が必要となるマーダーミステリーやマシュマロ・チャレンジです。少人数だからこそ、一人ひとりの発言や行動が重要性を増します。
また、2つの真実と1つの嘘のような自己開示ゲームも、少人数の方がじっくりと互いの話を聞き、深い関係性を築くことができるでしょう。時間をかけて一人ひとりの話に耳を傾けることで、大人数では得られない親密さが生まれます。
少人数ならではの利点を活かすコツは、全員が発言できる機会を確保することと、個々の強みが明確に発揮できるゲーム設計にすることです。大人数向けのゲームでも、ルールを少し調整することで少人数でも十分な効果が得られるようになります。
短時間で遊べるチームビルディングゲームは?
会議の合間や限られた時間内で実施できる短時間のチームビルディングゲームも多数あります。15分以内で完結するものとしては、バースデーラインや共通点探しゲームが最適です。これらは準備も最小限で、すぐに始められる利点があります。
30分程度の時間がある場合は、ペーパータワーやジェスチャーゲームも選択肢に入ります。これらは簡単な説明だけで開始でき、振り返りの時間も含めてコンパクトに実施することが可能です。
短時間のゲームでも効果を高めるためには、「このゲームを通じて何を学びたいか」という目的を明確にしておくことが重要です。また、後日の会議や業務の中で「あのゲームで学んだように…」と関連づけることで、短い体験からも長期的な効果を引き出すことができるでしょう。
室内で遊べるチームビルディングゲームはマダミスがイチオシ!

室内チームビルディングゲームの中でも、とりわけ高い効果を発揮するのがマーダーミステリー(マダミス)です。単なる娯楽要素だけでなく、コミュニケーション能力、論理的思考力、協調性など、ビジネスシーンで求められる多様なスキルを楽しみながら養うことができます。
特に、会社の課題や目標に合わせてカスタマイズされたシナリオを用いることで、より実践的な学びを得ることが可能です。例えば、部署間の連携強化が課題であれば、異なる情報を持つキャラクター設定にすることで、情報共有の重要性を体感できるでしょう。
また、マダミスは参加者全員が主体的に関わるため、普段発言の少ないメンバーも積極的に参加する姿が見られます。役割を演じることで普段とは異なる視点や発想が生まれ、チームに新たな可能性をもたらすこともあります。
効果的なチームビルディングのために、ぜひマーダーミステリーという選択肢を検討してみてはいかがでしょうか。
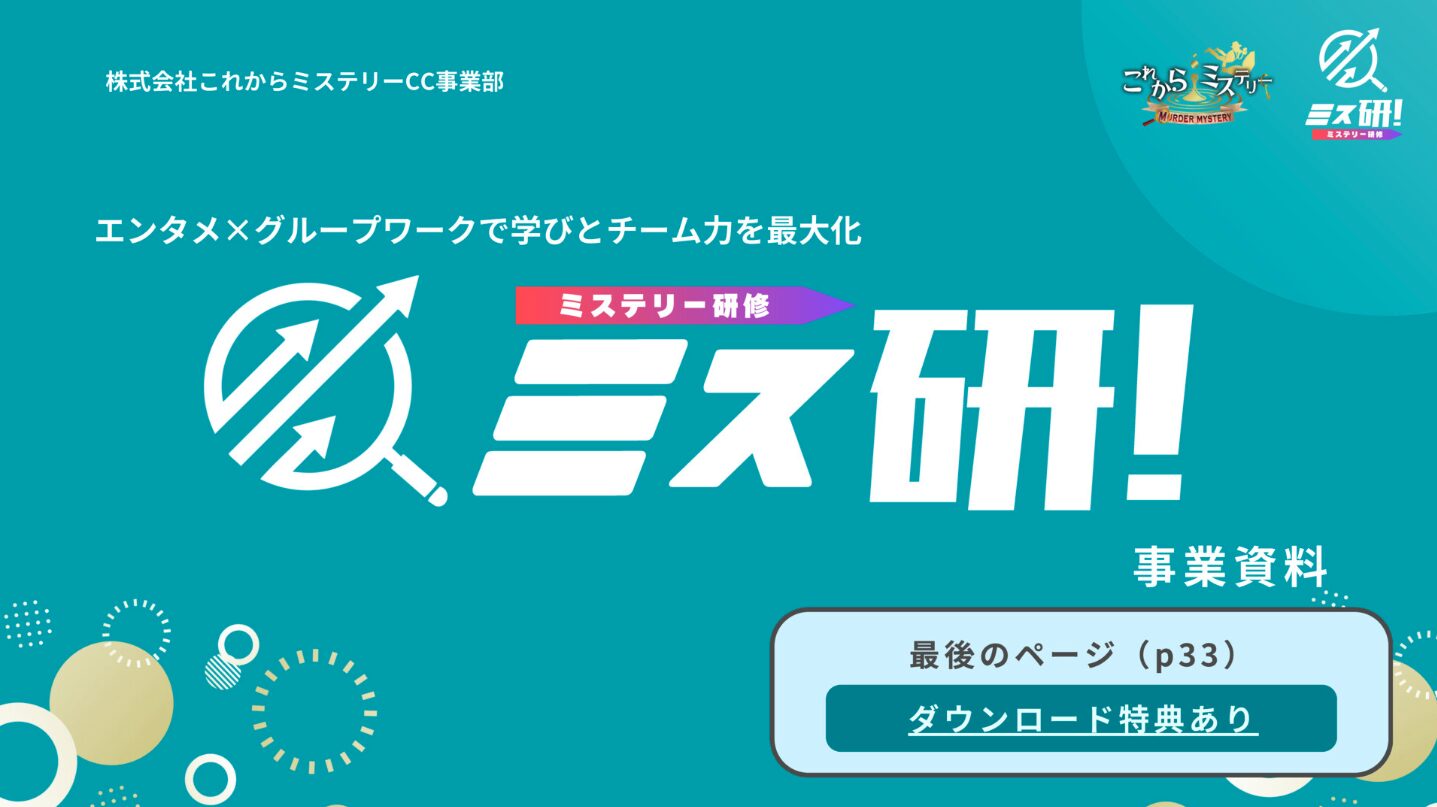
- これからミステリーは飯田祐基とヒカルがタッグを組んだマーダーミステリー専門の企業
- マーダーミステリーを絡めた「企業研修」や「企業PR」も可能!
- 社内コミュニケーションの活性化や企業の認知拡大におすすめ!
\認知を広げたいあなたに/